国・地域から調べる
留学先の国の特徴や留学情報をご紹介。
国ごとの違いを明確に知り、自分にあった留学先を見つけましょう。

アメリカ合衆国
体験レポート

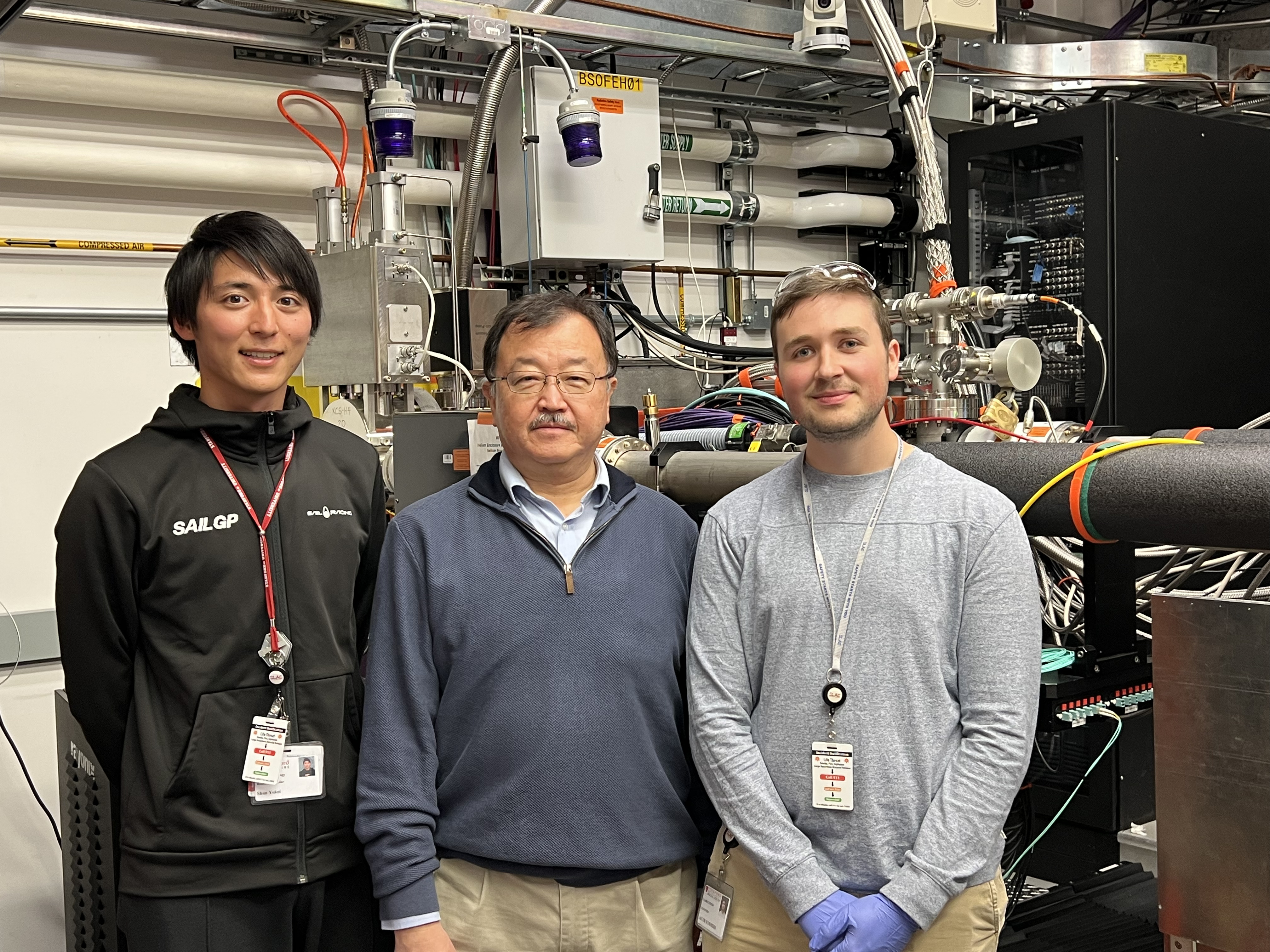
留学先国・地域:アメリカ合衆国・カリフォルニア州・スタンフォード
留学期間:2022年2月~2023年7月
学校名:Stanford University
専攻名:Department of Structural Biology, School of Medicine
留学形態:研究留学(日本の博士課程在籍中)
奨学金:トビタテ!留学JAPAN
留学期間:2022年2月~2023年7月
学校名:Stanford University
専攻名:Department of Structural Biology, School of Medicine
留学形態:研究留学(日本の博士課程在籍中)
奨学金:トビタテ!留学JAPAN
留学の動機について
Q. 留学をしようと思った動機を教えてください。
私は学部生の頃から、博士前期・後期課程で研究留学したいと考えていました。そのきっかけは、学部2年でのアメリカのジョージア州 アトランタへの短期留学です。アトランタでは約1ヶ月間、現地で語学学校に通いながら、食生活・文化などを学び、そして日本とアメリカの大学生が持つ、勉学に対する意識の違いや、博士課程に対する認識の違いを感じました。そこで、日本だけではなくアメリカなど国外の大学・大学院に身を置いて学びたいとより考えるようになりました。
私は学部生の4年間、体育会ヨット部で毎日セーリング漬けの生活だったため、海外大学院への進学は叶いませんでしたが、学部生の頃から語学力を磨き、TOEICやTOFELなどの資格試験を通じて英語力を高め、研究留学のために少しずつ準備してきました。
Q. 留学先の国・地域、留学先校を選んだ理由を教えてください。
小さい頃に、アメリカのテネシー州 ナッシュビルに半年間住んでいた経験や、学部課程2年次にアメリカのジョージア州 アトランタにホームステイをしていた経験があったので、自然とアメリカに留学したいと考えていました。
留学先を選ぶ際は、実験手法や計算手法を組合わせた研究を行っており、自分が修得したいと考えていた”シミュレーションを実験に応用する技術”を学ぶことができる環境を選びました。また、現地の交流で培われるスタンフォード大学の研究者との人的ネットワークも構築したかったので、留学先に選びました。
Q. 留学に対する家族の反応はどうでしたか?
家族は自分の留学の意図をとても理解してくれて、アメリカでとことんチャレンジしてきなさいという感じで応援してくれていたと思います。自分の父も留学経験があったのも理解が得やすかった要因だと思います。
私は学部生の頃から、博士前期・後期課程で研究留学したいと考えていました。そのきっかけは、学部2年でのアメリカのジョージア州 アトランタへの短期留学です。アトランタでは約1ヶ月間、現地で語学学校に通いながら、食生活・文化などを学び、そして日本とアメリカの大学生が持つ、勉学に対する意識の違いや、博士課程に対する認識の違いを感じました。そこで、日本だけではなくアメリカなど国外の大学・大学院に身を置いて学びたいとより考えるようになりました。
私は学部生の4年間、体育会ヨット部で毎日セーリング漬けの生活だったため、海外大学院への進学は叶いませんでしたが、学部生の頃から語学力を磨き、TOEICやTOFELなどの資格試験を通じて英語力を高め、研究留学のために少しずつ準備してきました。
Q. 留学先の国・地域、留学先校を選んだ理由を教えてください。
小さい頃に、アメリカのテネシー州 ナッシュビルに半年間住んでいた経験や、学部課程2年次にアメリカのジョージア州 アトランタにホームステイをしていた経験があったので、自然とアメリカに留学したいと考えていました。
留学先を選ぶ際は、実験手法や計算手法を組合わせた研究を行っており、自分が修得したいと考えていた”シミュレーションを実験に応用する技術”を学ぶことができる環境を選びました。また、現地の交流で培われるスタンフォード大学の研究者との人的ネットワークも構築したかったので、留学先に選びました。
Q. 留学に対する家族の反応はどうでしたか?
家族は自分の留学の意図をとても理解してくれて、アメリカでとことんチャレンジしてきなさいという感じで応援してくれていたと思います。自分の父も留学経験があったのも理解が得やすかった要因だと思います。
留学の準備について
Q. 留学の準備にはどのくらいの期間を要しましたか?留学を思い立ってから、実際に出発するまで、それぞれの準備段階にわけて教えてください。
実際の渡航までのスケジュールは以下のようでした。新型コロナウイルス感染症の影響により、留学しようと思い立ってから実際に渡航するまでに2年近くかかりました。
【2019年11月~ 12月】
・体育会ヨット部引退後に留学準備に本格的に取りかかる
・留学相談(カウンセリング)などで情報収集
・トビタテ!留学JAPANという奨学金制度を知り、応募することを決意
【2020年1月~ 3月】
・留学先の候補を探し、渡航候補先の研究主宰者(PI)に連絡を取り、受け入れについて相談
・トビタテ!留学Japanの応募書類の準備
【2020年4月~ 11月】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、トビタテ!留学Japan (13期)の選考中止
・留学したい気持ちは変わらなかったので、博士後期課程に進むために研究活動に専念
【2021年12月~ 2月】
・トビタテ!留学Japanが14期の募集を始めたので、再チャレンジ
・渡航先の再選定
【2021年3月~ 7月】
・トビタテ!留学Japanの書類・面接選考
・7月にはトビタテ!留学Japanの選考通過
・東京2020にボランティアとして参加
【2021年8月~9月】
・渡航先のPIと研究や留学準備に関する打ち合わせ
【2021年10月~2022年1月】
・必要書類を準備し、Visaの申請開始
・1月に大使館での面接を受け、Visa発給
【2022年2月】
・アメリカに渡航し、Stanford Universityで留学開始
Q. 留学情報の収集はどのように行っていましたか?使用したウェブサイト、雑誌、イベント、SNS(YouTube、Twitter等)などがあれば、あわせて教えてください。
留学したいと考え始めた際は、皆さんと同じように留学に関して右も左もわからない状態でした。そこで、まず最初に、私は所属大学の国際教育センターが主催している留学相談(カウンセリング)を利用して、留学に関する大まかな情報収集を行ないました。研究留学をどれくらいの期間行ったら十分なのか、どのような制度を利用して留学するのが良さそうなのかなど相談し、目標やスケジュールを立てて準備を行ってました。また、留学直前の現地の情報などは、トビタテ!留学JAPANのコミュニティなどを利用して、情報収集を行なっておりました。
Q. 語学学習はどのように行っていましたか?
英語に苦手意識があったので、学部1年生の頃からTOEICやTOFELなどの資格試験、オンライン英会話などを利用して、語学学習を行なっておりました。研究室に配属されてからは、学術論文を読む頻度や英語で発表を行う機会が増えたので、英語に触れる機会が増えました。また、所属大学でAcademic PresentationやAcademic Writingの授業を履修したりもしていました。
Q. 留学(斡旋)サービスなどは利用しましたか?
利用しませんでした。
Q. 留学の資金調達はどのように行いましたか?利用した奨学金などがあれば、あわせて教えてください。
留学中は、以下のような経費がかかりました。
(シリコンバレー近郊であり、世界でも物価・生活費が非常に高いため、あまり参考にならないかもしれません)
・1か月の家賃:$2200-2300
・1か月の生活費: $500-800
自費では長期留学することができなかったため、留学の際は、2022年2月から1年間はトビタテ!留学JAPANからの奨学金をいただき、残りの期間は国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST)の新たな国際頭脳循環モード促進プログラムという制度を利用して留学していました。また、所属大学の助手制度を利用して、専任助手としても勤務していました。
Q. 準備しておいてよかったこと、また準備しておいたほうがいいことなどはありますか。
もし英語圏に留学する場合は、自分の言いたいことが上手く伝えられなくても"へこたれない精神”を準備しておいた方が良いと思いました。私自身は、オンライン英会話などを通じて、講師とは不自由なく会話ができる状態で留学を開始しましたが、実際に現地で母国語を英語とする人達のグループに入ると、会話についていくのが精一杯で、なかなか会話に参加できませんでした。全然通用しなくて、落ち込む時期もありましたが、周りのサポートもあって逆境を乗り越えることができました。
精神面の準備することは難しいですが、できなくて当たり前だから、これからできるようになれば良いと前向きに考えるようにして、その経験を糧に頑張るための"へこたれない精神"を準備しておくことは大事だと思います。
Q. 入学や学生登録の手続き、ビザの手続きなどはどのように行いましたか。
特に苦労したことや気を付けたほうがいいことなどが教えてください。
Visaの申請や現地での研究員としての登録などに関しては、渡航先のスタッフが全て行なってくれたので、自分自身は必要事項の記入や必要書類を揃えるだけだったため、苦労は少なかったと思います。また、Visaの申請を4ヶ月前から始めていたので、手続きも時間の余裕を持って進めることができました。よく言われていることではあると思いますが、Visaの申請の際は自分の都合だけで進めることができないので、時間に余裕を持って進めた方がいいと思います。知人に自分と同じVisaを約1ヶ月で発給してもらった例もありますが(笑)
実際の渡航までのスケジュールは以下のようでした。新型コロナウイルス感染症の影響により、留学しようと思い立ってから実際に渡航するまでに2年近くかかりました。
【2019年11月~ 12月】
・体育会ヨット部引退後に留学準備に本格的に取りかかる
・留学相談(カウンセリング)などで情報収集
・トビタテ!留学JAPANという奨学金制度を知り、応募することを決意
【2020年1月~ 3月】
・留学先の候補を探し、渡航候補先の研究主宰者(PI)に連絡を取り、受け入れについて相談
・トビタテ!留学Japanの応募書類の準備
【2020年4月~ 11月】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、トビタテ!留学Japan (13期)の選考中止
・留学したい気持ちは変わらなかったので、博士後期課程に進むために研究活動に専念
【2021年12月~ 2月】
・トビタテ!留学Japanが14期の募集を始めたので、再チャレンジ
・渡航先の再選定
【2021年3月~ 7月】
・トビタテ!留学Japanの書類・面接選考
・7月にはトビタテ!留学Japanの選考通過
・東京2020にボランティアとして参加
【2021年8月~9月】
・渡航先のPIと研究や留学準備に関する打ち合わせ
【2021年10月~2022年1月】
・必要書類を準備し、Visaの申請開始
・1月に大使館での面接を受け、Visa発給
【2022年2月】
・アメリカに渡航し、Stanford Universityで留学開始
Q. 留学情報の収集はどのように行っていましたか?使用したウェブサイト、雑誌、イベント、SNS(YouTube、Twitter等)などがあれば、あわせて教えてください。
留学したいと考え始めた際は、皆さんと同じように留学に関して右も左もわからない状態でした。そこで、まず最初に、私は所属大学の国際教育センターが主催している留学相談(カウンセリング)を利用して、留学に関する大まかな情報収集を行ないました。研究留学をどれくらいの期間行ったら十分なのか、どのような制度を利用して留学するのが良さそうなのかなど相談し、目標やスケジュールを立てて準備を行ってました。また、留学直前の現地の情報などは、トビタテ!留学JAPANのコミュニティなどを利用して、情報収集を行なっておりました。
Q. 語学学習はどのように行っていましたか?
英語に苦手意識があったので、学部1年生の頃からTOEICやTOFELなどの資格試験、オンライン英会話などを利用して、語学学習を行なっておりました。研究室に配属されてからは、学術論文を読む頻度や英語で発表を行う機会が増えたので、英語に触れる機会が増えました。また、所属大学でAcademic PresentationやAcademic Writingの授業を履修したりもしていました。
Q. 留学(斡旋)サービスなどは利用しましたか?
利用しませんでした。
Q. 留学の資金調達はどのように行いましたか?利用した奨学金などがあれば、あわせて教えてください。
留学中は、以下のような経費がかかりました。
(シリコンバレー近郊であり、世界でも物価・生活費が非常に高いため、あまり参考にならないかもしれません)
・1か月の家賃:$2200-2300
・1か月の生活費: $500-800
自費では長期留学することができなかったため、留学の際は、2022年2月から1年間はトビタテ!留学JAPANからの奨学金をいただき、残りの期間は国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST)の新たな国際頭脳循環モード促進プログラムという制度を利用して留学していました。また、所属大学の助手制度を利用して、専任助手としても勤務していました。
Q. 準備しておいてよかったこと、また準備しておいたほうがいいことなどはありますか。
もし英語圏に留学する場合は、自分の言いたいことが上手く伝えられなくても"へこたれない精神”を準備しておいた方が良いと思いました。私自身は、オンライン英会話などを通じて、講師とは不自由なく会話ができる状態で留学を開始しましたが、実際に現地で母国語を英語とする人達のグループに入ると、会話についていくのが精一杯で、なかなか会話に参加できませんでした。全然通用しなくて、落ち込む時期もありましたが、周りのサポートもあって逆境を乗り越えることができました。
精神面の準備することは難しいですが、できなくて当たり前だから、これからできるようになれば良いと前向きに考えるようにして、その経験を糧に頑張るための"へこたれない精神"を準備しておくことは大事だと思います。
Q. 入学や学生登録の手続き、ビザの手続きなどはどのように行いましたか。
特に苦労したことや気を付けたほうがいいことなどが教えてください。
Visaの申請や現地での研究員としての登録などに関しては、渡航先のスタッフが全て行なってくれたので、自分自身は必要事項の記入や必要書類を揃えるだけだったため、苦労は少なかったと思います。また、Visaの申請を4ヶ月前から始めていたので、手続きも時間の余裕を持って進めることができました。よく言われていることではあると思いますが、Visaの申請の際は自分の都合だけで進めることができないので、時間に余裕を持って進めた方がいいと思います。知人に自分と同じVisaを約1ヶ月で発給してもらった例もありますが(笑)
留学中の様子について
Q. 留学中の学校生活はどうでしたか?海外の学校だからこそ苦労することや、逆に学校生活での楽しみなどを教えてください。
スタンフォード大学での研究活動を通じ、共同研究を始めるまでの”速さ”と、共同研究の”多さ”の違いを感じました。スタンフォード大学では、共同研究の文化がとても強く、自分たちの研究室ではできないけど必要な実験があったら、次の週にはその実験ができる研究室とコラボレーションしているようなスピード感でした。また、研究の資金の違いもすごく大きいと感じました。日本で研究していた時には、研究資金に関してあまり考えることはなかったのですが、仮説を実証するために必要な最も効果的な実験をスムーズに進めていくためには研究資金も大事な要素の一つであると留学中に考えさせられました。
また、スタンフォード大学では(他の大学のことはあまり分かりませんがアメリカ全体的に?)女性研究者が非常に多いことも驚きでした。私が研究していた建物の同じフロアだけでも、半数近くが女性研究者でした。最近は日本でも女性が活躍しやすい取り組みが少しずつ増えているように感じていましたが、ベイエリアと比較すると、日本の女性の活躍の場がかなり少ないことを身をもって感じました。
Q. 学校外の生活はいかがでしたか?寮などでの生活や休日の過ごし方に加えて、街の治安などについても教えてください。
研究活動以外には、現地の様々な団体が企画しているイベントやセミナー、コミュニティの活動に参加して、日本ではこれまで出会うことがなかった様々な人たちとの出会いがありました。日本人が少ない環境で交友関係を広げていく場合、最初の一人目を探すのは大変でした。しかし、一度数人の交友関係が広がると色々な人々同士が繋がっていき、まるで蜘蛛の巣を張り巡らすようにベイエリアにオフラインでの人的ネットワークが構築されていくように感じました。またベイエリアにいる日本人は同じような悩みを抱えている人が多く、出会ったばかりの人でも親身になって悩みや相談にのってくれ、人の温かさも感じました。
また、スタンフォード大学ではスポーツを通じた交流も非常に活発でした。キャンパス内にはサッカー場やテニスコート、ゴルフ場、スポーツジム、陸上コート、また収容人数5万人のスタジアムまでも完備されています。そういった施設はいつでも無料で使えるため(スタジアムは流石に無理でした…)多くの学生や研究者、その家族が利用しています。
特に、私は現地のサッカーチームに所属し、Intermural leagueと呼ばれる大学が主催するスポーツトーナメントやStanford Sunday Leagueと呼ばれる学期を通したリーグ戦などに参加し、スポーツを通じても様々な学部生・大学院生、研究者と親しい関係を築くことができました。スポーツの場合、お互いの身分を知らないままやることが多いので、仲良くなった後で何をしているのか聞いたら大学の教授だったなんてこともありました(笑)
Q. 留学中の生活で大変だったことを教えてください。また、それをどのように克服、対応しましたか?
留学中の生活で大変だったことは、経済的な困難です。ありがたいことに、トビタテ!留学JAPANなどの奨学金はいただいていたのですが、私が留学したスタンフォード大学周辺は、物価が世界的にも非常に高いことで知られており、ルームシェアの家賃が$2000ドル以上(日本円で30万以上)したため、生活費を捻出することが大変でした。
克服することはなかなか難しかったのですが、生活のやりくりする力がつきました。例えば、ジャガイモも食べることが多かったのでジャガイモを使った料理が得意になりました(笑)こういった経験も今では笑い話にできるようになったので、当時はとても大変でしたが人生の糧になったと考えております。
Q. アルバイトやインターンはしていましたか?
留学中は、アルバイトやインターンはしておりませんでしたが、所属大学の専任助手として勤務しておりました。
スタンフォード大学での研究活動を通じ、共同研究を始めるまでの”速さ”と、共同研究の”多さ”の違いを感じました。スタンフォード大学では、共同研究の文化がとても強く、自分たちの研究室ではできないけど必要な実験があったら、次の週にはその実験ができる研究室とコラボレーションしているようなスピード感でした。また、研究の資金の違いもすごく大きいと感じました。日本で研究していた時には、研究資金に関してあまり考えることはなかったのですが、仮説を実証するために必要な最も効果的な実験をスムーズに進めていくためには研究資金も大事な要素の一つであると留学中に考えさせられました。
また、スタンフォード大学では(他の大学のことはあまり分かりませんがアメリカ全体的に?)女性研究者が非常に多いことも驚きでした。私が研究していた建物の同じフロアだけでも、半数近くが女性研究者でした。最近は日本でも女性が活躍しやすい取り組みが少しずつ増えているように感じていましたが、ベイエリアと比較すると、日本の女性の活躍の場がかなり少ないことを身をもって感じました。
Q. 学校外の生活はいかがでしたか?寮などでの生活や休日の過ごし方に加えて、街の治安などについても教えてください。
研究活動以外には、現地の様々な団体が企画しているイベントやセミナー、コミュニティの活動に参加して、日本ではこれまで出会うことがなかった様々な人たちとの出会いがありました。日本人が少ない環境で交友関係を広げていく場合、最初の一人目を探すのは大変でした。しかし、一度数人の交友関係が広がると色々な人々同士が繋がっていき、まるで蜘蛛の巣を張り巡らすようにベイエリアにオフラインでの人的ネットワークが構築されていくように感じました。またベイエリアにいる日本人は同じような悩みを抱えている人が多く、出会ったばかりの人でも親身になって悩みや相談にのってくれ、人の温かさも感じました。
また、スタンフォード大学ではスポーツを通じた交流も非常に活発でした。キャンパス内にはサッカー場やテニスコート、ゴルフ場、スポーツジム、陸上コート、また収容人数5万人のスタジアムまでも完備されています。そういった施設はいつでも無料で使えるため(スタジアムは流石に無理でした…)多くの学生や研究者、その家族が利用しています。
特に、私は現地のサッカーチームに所属し、Intermural leagueと呼ばれる大学が主催するスポーツトーナメントやStanford Sunday Leagueと呼ばれる学期を通したリーグ戦などに参加し、スポーツを通じても様々な学部生・大学院生、研究者と親しい関係を築くことができました。スポーツの場合、お互いの身分を知らないままやることが多いので、仲良くなった後で何をしているのか聞いたら大学の教授だったなんてこともありました(笑)
Q. 留学中の生活で大変だったことを教えてください。また、それをどのように克服、対応しましたか?
留学中の生活で大変だったことは、経済的な困難です。ありがたいことに、トビタテ!留学JAPANなどの奨学金はいただいていたのですが、私が留学したスタンフォード大学周辺は、物価が世界的にも非常に高いことで知られており、ルームシェアの家賃が$2000ドル以上(日本円で30万以上)したため、生活費を捻出することが大変でした。
克服することはなかなか難しかったのですが、生活のやりくりする力がつきました。例えば、ジャガイモも食べることが多かったのでジャガイモを使った料理が得意になりました(笑)こういった経験も今では笑い話にできるようになったので、当時はとても大変でしたが人生の糧になったと考えております。
Q. アルバイトやインターンはしていましたか?
留学中は、アルバイトやインターンはしておりませんでしたが、所属大学の専任助手として勤務しておりました。


留学後について
Q. 留学を経験してみて感じたこと、学んだことはありますか?
留学を通じて、常に不測の事態に動じない心の持ち方をできるようになり、自分自身の成長を感じました。
コロナ禍前であれば、留学の1年程前から様々な準備を始め、大体のことがスケジュール通りに進み、予定通り留学できることが当たり前だったと思います。しかし、私も含めてコロナ禍で留学をしようとした場合、自分自身では解決できない様々な不測の事態が発生し、思い通りに進まないことが多々ありました。例えば、元々、トビタテ!留学JAPAN 13期生として博士前期課程で留学したいと考えていましたが、コロナ禍により選考が急遽中止になったり、各国の感染状況により留学時期・期間の延長も余儀なくされました。留学が思い通りに進まずに悶々とする時期もありました。しかし、留学したいという思いは変わることがなかったので、これら全て含め留学準備であると捉え方を変え、また、海外ではもっと不測の事態が起こるので自分への試練だと考えられるようになり、常に物事をポジティブに捉えるようになりました。留学中や留学後も不測の事態はたくさんあって、留学前であれば、あたふたしてしまったと思いますが、今は身についた常に動じない心の持ち方によって、そういった焦りの感情が減り、物事を常に冷静に捉えられるようになりました。
Q. 留学後の進路について教えてください。
留学後の現在は、所属大学の博士後期課程を修了するために研究に取り組んでいます。将来は海外の研究機関でチャレンジしたいと考えているので、残りの博士後期課程の期間でしっかりと実力をつけ、博士号取得後に海外挑戦したいと思います。
Q. 最後にこれから留学をする方へのメッセージ・アドバイスをお願いします。
これから留学を検討している方がもし読んでいらっしゃったら、自分からのアドバイスとして、”できるだけ早く、可能な限り長い期間”留学した方がいいと思います。自分自身は約1年半の留学だったので、こういったアドバイスが適切なのかわかりませんが、留学による経験を通じて、より物事を多角的に捉えることができるようになり自分自身の価値観を良い意味で広げる(変える)ことができると思います。例えば、世界から日本を客観的に見ることで、普段あまり考えることがないような日本の真の魅力や社会課題に気づくこともあるかと思います。こういった経験はできるだけ早くした方が良いし、長く滞在すれば気づく機会も必然と増えると思うので、個人的にはできるだけ早く、可能な限り長い期間の留学をおすすめします。
留学を通じて、常に不測の事態に動じない心の持ち方をできるようになり、自分自身の成長を感じました。
コロナ禍前であれば、留学の1年程前から様々な準備を始め、大体のことがスケジュール通りに進み、予定通り留学できることが当たり前だったと思います。しかし、私も含めてコロナ禍で留学をしようとした場合、自分自身では解決できない様々な不測の事態が発生し、思い通りに進まないことが多々ありました。例えば、元々、トビタテ!留学JAPAN 13期生として博士前期課程で留学したいと考えていましたが、コロナ禍により選考が急遽中止になったり、各国の感染状況により留学時期・期間の延長も余儀なくされました。留学が思い通りに進まずに悶々とする時期もありました。しかし、留学したいという思いは変わることがなかったので、これら全て含め留学準備であると捉え方を変え、また、海外ではもっと不測の事態が起こるので自分への試練だと考えられるようになり、常に物事をポジティブに捉えるようになりました。留学中や留学後も不測の事態はたくさんあって、留学前であれば、あたふたしてしまったと思いますが、今は身についた常に動じない心の持ち方によって、そういった焦りの感情が減り、物事を常に冷静に捉えられるようになりました。
Q. 留学後の進路について教えてください。
留学後の現在は、所属大学の博士後期課程を修了するために研究に取り組んでいます。将来は海外の研究機関でチャレンジしたいと考えているので、残りの博士後期課程の期間でしっかりと実力をつけ、博士号取得後に海外挑戦したいと思います。
Q. 最後にこれから留学をする方へのメッセージ・アドバイスをお願いします。
これから留学を検討している方がもし読んでいらっしゃったら、自分からのアドバイスとして、”できるだけ早く、可能な限り長い期間”留学した方がいいと思います。自分自身は約1年半の留学だったので、こういったアドバイスが適切なのかわかりませんが、留学による経験を通じて、より物事を多角的に捉えることができるようになり自分自身の価値観を良い意味で広げる(変える)ことができると思います。例えば、世界から日本を客観的に見ることで、普段あまり考えることがないような日本の真の魅力や社会課題に気づくこともあるかと思います。こういった経験はできるだけ早くした方が良いし、長く滞在すれば気づく機会も必然と増えると思うので、個人的にはできるだけ早く、可能な限り長い期間の留学をおすすめします。
日本学生支援機構
(JASSO)とは
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、
文部科学省が所管する団体です。
学生支援を先導する中核機関として、「奨学金事業」
「留学生支援事業」および
「学生生活支援事業」を
総合的に実施し、
次世代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材を育成すると
ともに、
国際理解・交流の促進を図ることを目指しています。
文部科学省が所管する団体です。
学生支援を先導する中核機関として、「奨学金事業」
「留学生支援事業」および
「学生生活支援事業」を
総合的に実施し、
次世代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材を育成すると
ともに、
国際理解・交流の促進を図ることを目指しています。


